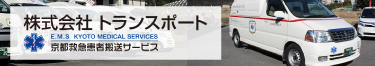栄養管理室
管理栄養士は、専門的な知識や技術で一人一人に合わせた栄養指導や給食管理・栄養管理を行います。 病院では、患者さんの疾患・病状に合わせた栄養指導や、病院の食事がとりづらい方に食事調整などを行う栄養管理が主な業務です。医師、看護師、その他の医療職種とともに、治療・合併症の予防、低栄養の予防など、患者さんに適切な栄養サポートを行います。 入退院支援センターでは、食物アレルギーや栄養状態、嚥下状態などの情報を事前に聞き取り、入院中の栄養管理に役立てています。また退院時には、転院先や訪問看護ステーション、ケアマネジャーに入院中の栄養管理情報を提供するなど、退院支援にも力を入れています。
所属長のひとこと

主席課長
長谷川 由起(はせがわ ゆき)
栄養管理室では、患者さんの気持ちに寄り添い適切な栄養サポートを行っています。食事や栄養面について、心配なことや困っていることがありましたら、管理栄養士にお声掛けください。
スタッフ紹介(2023年11月現在)
管理栄養士:14人、事務職員(栄養士):1人

- 日本糖尿病療養指導士:2人
- 栄養サポートチーム(NST)専門療法士:5人
- 心臓病療養指導士:2人
- 腎臓病病態栄養専門管理栄養士:1人
業務内容
食事提供
医師の指示のもと、患者さん個々の状況に応じた栄養管理計画を立て、計画に見合った食事提供を目指しています。特別な制限のない一般食と、疾患の治療のための食事である特別治療食があります。
酵素を使った調理法を導入し、“肉の硬さ“や”魚のパサつき“に配慮した料理の提供を行っております。その他にも、色合いの改善や人気メニューを増やすなどの工夫を行っています。
栄養管理
患者さん一人一人の病状や身体状況に合わせて、病気の治療、合併症や低栄養の予防に必要な食事の提供、栄養に関する指導、助言を行っています。
医師、看護師、薬剤師やその他医療スタッフと連携し、カンファレンスに参加し、必要な方にはNST(栄養サポートチーム)回診、緩和ケア回診を行い、食形態の変更、自助食器や食具の提案、栄養補助食品の提案など栄養面のサポートを行っています。
栄養指導
心臓病や糖尿病などの生活習慣病の療養には食事療法がとても重要です。また、手術後には、術後の栄養管理のための適切な食形態や食品の選択、栄養状態の維持などの栄養療法が大切です。嚥下障害には適切な食品の選択や簡便な調理法、低栄養やがん治療中のときには、体を維持するために食べやすい食品の選択など、患者さん一人一人の思いを受け止めながら、状況に合った食事内容の提案を行うようにしています。
入院中のみならず、外来・心臓リハビリテーションでご通院中の患者さんを対象に、医師の指示に基づき管理栄養士が個別に栄養指導を随時行っています。ご本人が対象ですが、ご家族にも同席いただけます。
実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
|---|---|---|---|
| 個別栄養指導件数 | 1,584 | 2,955 | 3,446 |
| NST回診件数 | 410 | 450 | 502 |