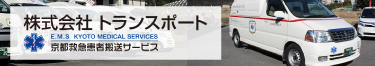救命救急センター・京都ER
当センターはER型救急診療を実践しています。ER型というのは救急担当医が専門分野にか かわらず全科の救急疾患に関わり、必要に応じて専門医に引き継ぐ体制のことです。どんな病 態でも対応できる柔軟な救急診療を心掛けています。2012年、当センターは行政から救急医 療の業績を評価され、近畿では初めて民間病院の救命救急センターに指定されました。これを 受けて当院では救急専用病棟を設け、さらに救急体制の強化と円滑化を図るとともに地域の救 急医療の中核施設としての役割を担うべく防災活動やドクターカー搬送なども積極的に行って いきます。
診療内容
当センターでは、成人の感冒、夜間の腹痛症状や突然の胸痛発作、高齢者の急な発熱や小児のひきつけ、さらに、熱傷や薬物中毒、交通事故や転落などによる多発外傷、心肺停止症例まで、重症度や疾患の特殊性に関係なく、あらゆる救急疾患を扱っています。
当センターがめざす救急医療は「患者さんの立場に立った救急」。“拒否しない救急”から、さらに発展して“救急診療の質の向上”を目指し診療に当たっています。どんな病態でも対応できる柔軟な救急診療を心掛けています。
他科のバックアップ
総合内科・ICUはもちろん、全科の24時間オンコール体制があり、バックアップは万全です。 夜間の救急患者さんは全て、担当医の判断で救命救急病棟に入院可能となっており、翌日に各科と連携します。
対応疾患
- 感冒、腹痛、下痢、発熱などの疾患
- 角膜炎、結膜炎
- へんとう腺炎、鼻出血、中耳炎、耳鳴り、突発性難聴
- 湿疹、じんましん
- 尿路結石、性病、前立腺炎
- 下腹部痛や切迫流産
- 小児科の発熱、腹痛、熱性けいれん
- めまい、頭痛、意識障害
- 交通外傷や転倒などによる打撲、脱臼、骨折
- 不整脈、狭心症、心筋梗塞、心不全
- 消化器潰瘍、肝硬変、膵炎、胆石症
- 虫垂炎、ヘルニア陥入、腸閉塞、消化器穿孔
- 大動脈解離、動脈瘤切迫破裂
- 交通外傷や転落事故などによる多発外傷
- 薬物中毒
- 熱傷(重症度に関わらず、初期対応は全ての症例に行う)
- 心肺停止
2022年の診療実績
救急車搬入患者数:7,200人(1日平均:19.7人)
- 呼吸器系疾患:915件
- 内科系疾患:784件
- 外科系疾患:637件
- 整形系疾患:527件
- 循環器系疾患:446件
- 消化器系疾患:424件
- 尿路性器系疾患:399件
- 内分泌系疾患:287件
- 頭部外傷:238件
- 神経系疾患:237件
- その他:220件
- 誤嚥性肺炎:213件
- 心不全:200件
- 頭部挫創:195件
- 大腿骨転子部骨折:191件
- 脳梗塞:182件
- 心肺停止(蘇生分含む):151件
- 悪性新生物:149件
- 頭蓋内損傷:137件
- 精神系疾患:130件
- 末梢性めまい症:122件
- 整形外科疾患:95件
- 急性肺炎:88件
- 急性心筋梗塞:81件
- 急性胃腸炎:79件
- 熱性痙攣:73件
- 救急受診人数:22,601人(1日平均:61.9人)
- 救急から集中治療室への入院数:282人