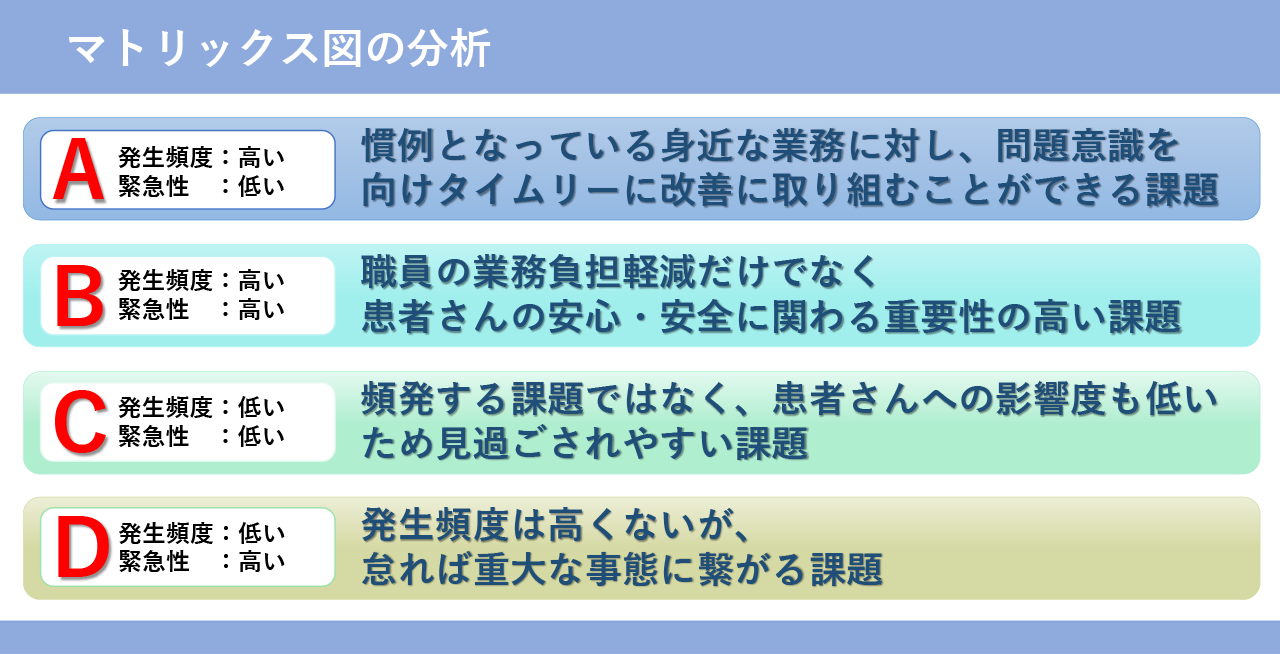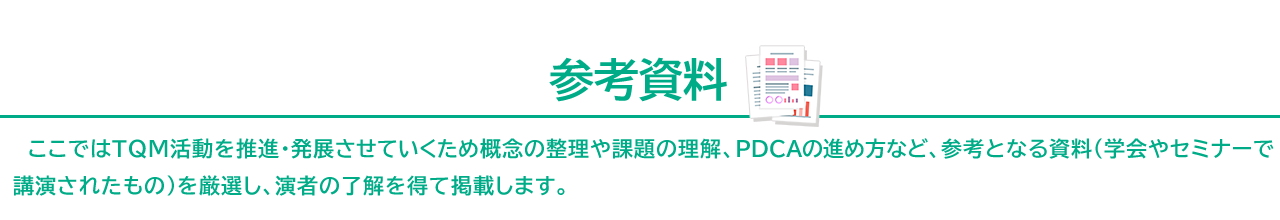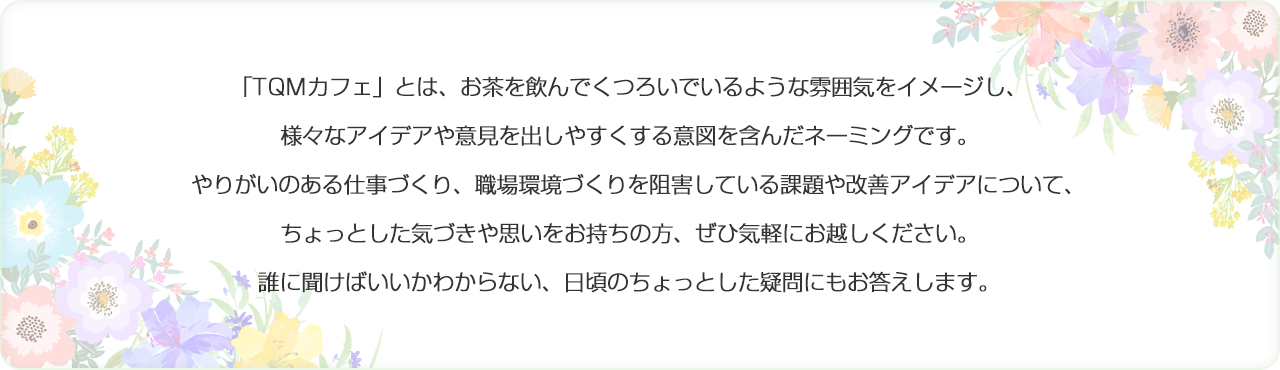TQM(Total Quality Management)とは、全員・全体(Total)で、医療・サービスの質(Quality)を、継続的に向上させる(Management)ことです。実際の活動には、「QC 手法(QC=Quality Control)」と呼ばれる手法を用います。 医療・介護現場はとても忙しく、現場でなければ気付けないムダ・ムリ・ムラが置き去りにされています。現場の気付きを大切にし、諦めずに改善していくことが重要です。当センターは、現場の課題に対して多くの視点で改善策を考え実行できるように支援します。ムダ・ムリ・ムラが解消できれば患者さんに寄り添う時間を増やし、(= 患者さんも職員もスマイル)現場の働き方を変える(= 職員も家族もスマイル)ことができます。
業務改善の視点

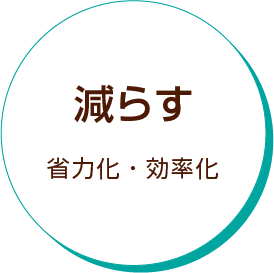

業務改善進行フロー

洛和会のパーパスとTQM

2022年10月~11月に実施した「提案」アンケート調査に多くの職員の皆さまにご回答をいただき、ありがとうございました。TQM支援センターではよりよい働き方をめざし、職場環境の改善を行うためにTQM活動を推進しております。
今回のアンケートの目的は、業務改善したいと思っていることをできるだけ具体的に自由に記載していただき、現場の顕在化・潜在化した課題を可視化し、TQM活動の発展に役立てていくものです。
アンケート内容を考察し、まとめましたのでご報告いたします。
- 資料1 アンケート結果の分析・考察方法について概要 (PDF[191KB])
- 資料2 アンケート回答内訳 (PDF[107KB])
- 資料3 回答者の大分類内訳(図) 回答内容分類内訳(図) (PDF[178KB])
- 資料4 アンケート内容から抽出した改善課題 (PDF[289KB])
自由記載の内容を同じキーワード、同類の内容に仕分けし、5つに分類しました。
- A)残業、勤務時間、勤務体制に関すること
- B)日々実践している自分(自部署)の業務の問題とその具体的な方策やアイデアに関すること
- C)上司・同僚との関係性や職場風土に関すること
- D)就業規則や法的根拠について理解不足
- E)愚痴や批判
分類したほとんどの内容は、日々の業務量の多さ、ムダな業務、慣例的な業務、ローカルルールを指摘し、何をどのように変えればよいか具体的な対策案が提案してあるものが多くありました。
職場の上司や同僚と関係性については潜在化していた感情的な問題が浮き彫りになっています。愚痴・批判的内容の記載があることは、発言しない・発言できないという組織として危険な状況ではないことを示しており、見方を変えた業務改善への意見として捉えたいと考えます。
以上のように分類し見えてきた業務改善の内容を概念化し、個人の問題ではなく全体の課題として取り組む業務改善課題として資料4に整理しました。今後、関係部署に共有しTQM活動の課題としてつなげていきたいと考えます。
洛和会丸太町病院
テーマ
丸太町HPとお友達になって知ってもらおう!LINE始めました!
課題
もっと洛和会丸太町病院のことを知ってもらいたい、伝えたいという想いはあるが特化した情報発信コンテンツがホームページしかなかった。院内にWi-Fiを設置することをきっかけにスマホアプリのLINEでお友達になってもらう取り組みを行った。
実施策
- 患者さんへ情報発信に関するアンケートを実施し、スマートフォンで気軽に確認できるコンテンツであれば使用したいという声が多いことがわかった
- 洛和会丸太町病院公式LINE開設
- 周知方法
- 外来、病棟へポスターの掲示、声かけ
- 入院のしおりに案内を挟み込み
- 情報内容はすでにホームページや各診療科が公開したものを再発信することにし発信した情報について良かったか等アンケート調査を実施し発信する情報内容を吟味した
- 発信した情報コンテンツ(例)
- 各診療科の医師の顔も見ることができる「地域連携ニュース」
- 地域交流イベント「メディカルフェスティバル開催について」
- 糖尿病患者さんだけでなく糖尿病を予防したい方へも食材選びのポイントなどがわかる「糖尿病だより」
- 健康にまつわる役立つ情報を分かりやすく解説する「京の健康らくわラジオ」など
成 果
- LINE開設以降ひと月に約50名友達登録数が増加している
- これまで知らなかった洛和会丸太町病院の情報に辿り着けたと喜びのお声をいただいた
- 色々な勉強会など多岐にわたる情報発信を楽しみにしているとの激励のお声をいただいた
- 各診療科の先生の紹介やマイナンバー保険証の情報等の要望もいただき、さらに洛和会丸太町病院に興味をもってもらうことができた
現在はLINEを活用して患者さんと一緒に行う医療安全活動について取組中です。今後も注目の業務改善をぜひご確認ください!!
- 2025年1月:【医療DX】電子カルテ情報の標準化
- 2024年11月:TQM活動における効果測定「定量評価・定性評価」の指標
- 2024年10月:介護で働く外国人職員の雇用と定着の促進についての資料
- 2024年5月:令和6年度 診療報酬改定説明資料
- 2024年1月:管理職のマネジメント能力
- 2023年11月:TQM活動に活用できる統計テクニック
- 2023年9月:ICT活用事例集 ~ICT活用でどんな可能性が広がるのか~
- 2023年7月:職員が健康で安心して働くことができる職場環境づくりのヒント
- 2023年6月:新型コロナウイルス感染症 5類感染症移行後の対応について
- 2023年5月:実践的な動画で学ぶ改善のノウハウ ~効果的な業務改善のヒント~
- 2023年3月:業務改善の図解
- 2023年2月:医療DXの実現に向けた取り組みについて
- 2023年1月:改正感染症法について
- 2022年12月:感染症法等の一部を改正する法律案について
- 2022年11月:押印の廃止に関する見解について
- 2022年10月:働き方改革の基になる業務の見直し類型について
- 2022年9月:電子帳簿保存法改定について
- 2022年9月:成果を挙げるチーム作りに必要な心理的安全性の確保
- 2022年8月:観光庁「宿泊業の生産性向上事例集」
- 2022年6月:「朝課外」廃止の動きの広がり